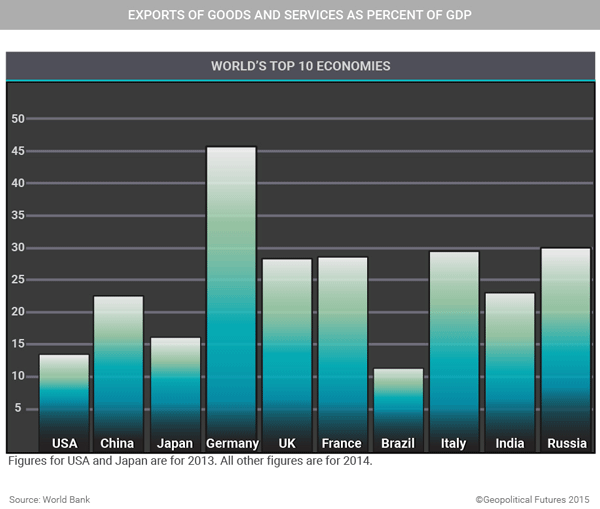Part One —
Insight as Activity(行為としての閃き)
Ch1 Elements(要素)(101102_00:49:40)
われわれがルネッサンスと呼ぶ人間の心が広く深くかき乱されたその真ただ中にあって、デカルトは、あまりにも多くの人が自分の努力を一見してつまらない問題に向けるのは人として似つかわしくない、と確信していた。デカルトの『才能を導く原則』という書物の中で何回もこのテーマを取り上げている。数学、科学の諸分野そして哲学の諸分野に精通することは、時間をかけた小さな閃きの地道な蓄積の結果である。大きな問題は小さな問題に分けることで解決される。天才の発想は絶え間なく探求するという習性の結果に過ぎない。その探求が、誰にでも理解できるシンプルな事柄に含まれるすべてを、明晰かつ判明的に把握させる。
私は有名な数学者であり哲学者であるデカルトのその確信を思い出すことによって、この書を始めることが良いと思った。なぜなら我々の最初の仕事は、閃きと言う言葉で何が意味されるのかについて慣れ親しんでもらうことにある、と思うからである。そしてその目的に達するための唯一の道は、その特徴はつまらないものであるが、一連の実例に間近に接し注視することである。
1.劇的な実例
我々が示す最初の実例は、アルキメデスがシラクーザの浴場から謎の言葉「ユーリカ(見つけた)」と発しながら裸で飛び出した物語である。ヒエロ王は、まれに見る熟練のしかし正直者かどうか疑わしい職人が作った王冠を奉献されたとき、その金の王冠に質の悪い金属が加えられていないかどうか知りたくて、アルキメデスにその解決を求めた。アルキメデスは、お風呂に入っているとき急に解決策が閃いた。それは冠を水の中で計りなさい、ということだった。その指示の裏には比重と体積による水の排斥量の原理が隠れている。
流体静力学の個々の原理について、われわれが直接関わる必要はない。なぜなら、我々の目標は閃きについての閃きだからである。アルキメデスは冠について考えることによって、閃きを得た。そこで我々はアルキメデスについて考えることで、われわれの閃きを得る必要がある。我々が閃きについて把握しなければならないことは、閃きは(1)探求時の緊張が解けるときに起こる、(2)急にそして不意にやって来る、(3)外的環境の作用としてではなく、内的状態の作用である、(4)具体的な事柄と抽象的な事柄の間を旋回する、(5)自分の心の習慣的特性の中に残る、ということである。(注記1)
まず、第一の閃きの特徴、探求時の緊張が解けるときに起こる、ということについては、アルキメデスの押さえきれない特徴的な歓喜の叫びの物語において劇的に表現されている。けれども、ここで私が言いたいポイントは特徴的な喜びのことではなくて、その前にあった欲求や努力について示すことである。普通の科学者が成功したときの満足感はもっと平静なものであるが、その科学者の探求の熱意はアルキメデスのそれを超えている。他の欲求の声(雑音)が静まっているとき、我々みんなの深いところで、知る、理解する、疑問をもつ、理由を発見する、原因を見つける、そして説明することに駆り立てているものがある。その駆り立てているものはいろいろの名前で呼ばれているが、それが正確にその本質が何であるのかは議論すべき項目である。けれども、それらが探求するという行為であることについては疑問の余地はない。そしてそれは人を夢中にさせ、何時間でも、毎日でも、何年でも、狭い牢獄のような自分の書斎や研究室に人を閉じ込めてしまうことができる。それは人を危険な探検の旅に送り出し、他の関心事、他の追跡、他の研究、他の職業、他の快楽、他の功績から人を遠ざけてしまうこともできる。それは目覚めている間の人の意識を埋め尽くし、世間の普通の事を見えないように覆い隠し、眠っている時は夢の世界にまで侵入してくる。それは何ら後悔の念をもたらすことなく、単に成功の希望のみがあるだけで確実に約束されたわけでもないにも関わらず、終わりの無い犠牲を強いる。この理解し難く、急に、傲慢に欲求してくるもののシンボルとして、「私は手に入れた」と裸で走りながら興奮して叫ぶ男ほど、より良いシンボルは見いだせないであろう。
第二は、閃きは突然に思いがけないときに起こるという特徴である。アルキメデスが彫刻『考える人』が表現している気分と姿勢でいるときには、その閃きは起こらなかった。それはフラッシュのように急に、どうでもいい時に、そしてリラックスした時に起こる。もう一度、閃きの普遍的な側面をドラマチックに表現してみましょう。最終的な分析によれば、閃きに達するにはルールを学ぶこと、教訓・命令に従うこと、そして方法論を勉強することによってではない。閃きに達するには発見が新たな出発点となり、それが新しいルールの始まりとなることによってであり、それが古いルールを補いあるいはそれに取って代わることさえある。天才というのは独創的である。定められたルーチンを無視し、未来のルーチンとなる新しい繋がりを生み出すからこそ天才である。もしも発見のためのルールがあるとすれば、発見はそのとき単なる推論となるだろう。天才になるためのルールがあるとすれば、そのとき天才たちは三文文士(hack)となる。本当のところ、発見に関する真実は教育の場で発見を伝達する場合においても真実である。というのは、先生は生徒が理解することを請け負うことができないからである。先生にできることは、問題の中の理にかなった要素を適切な重点配分とともに示唆にとんだ順序で紹介することだけである。そして理解への到達は生徒次第であり、生徒たちの理解に達する早さと容易さの程度は様々である。ある生徒は先生の解説が終わる前にポイントを把握し、別の生徒は先生のペースに丁度間に合っている。また、さらに他の生徒は問題について自分でもう一度復習したときにやっと光(問題の解決)を見る。最後に、何人かの生徒たちは全く理解に達せず、しばらくの間は授業に出てくるが、遅かれ早かれ落ちこぼれてしまう。
第三は、閃きは関数のようなものであり、それも外部環境ではなく人の内部条件の関数であるという特徴がある。多くの人は流体静力学の原理を把握することなくシラクーザの浴室をしばしば訪れていた。しかし、水に触れ、それが熱いか、冷たいか、それともぬるま湯かが分からずに入浴した人は誰一人無かったでしょう。そのことは、閃きと知覚の間に奇妙な違いがあることを示しています。人は耳が不自由でない限り、聴くことを避けることはできない。人は盲目でなければ、目を開きさえすれば見ることができる。知覚およびその知覚の内容は外部環境との瞬時の相関関係に基づいている。しかし、閃きにおいてはその人の内部状況が最重要である。それは、閃きは生まれつきの素質に依存し、そしてかなりの正確さで、閃きは賢明な人にはしばしば出現し、愚かなものには滅多に現れない、と言うことが出来る。さらに、閃きは習慣的志向、すなわち絶えず注意して「なぜ」と小さな質問を投げかけるかどうかに係っている。最後は、閃きは問題の的確な表現ができるかどうかである。もしヒエロ王がアルキメデスに彼の問題を投げかけなかったとしたら、もしかしてアルキメデスが自暴自棄になって真剣に考えなかったとしたら、シラクーザの浴室での出来事が他のどんなものよりも有名になることはなかったであろう。
第四は、閃きは具体的なものと抽象的なものとの間を旋回するという特徴がある。アルキメデスの問題は具体的であった。彼はある特定の王冠が純粋な金で作られたものかどうかの決着をつけなければならなかった。アルキメデスの解決法は具体的で、それは水の中で王冠の重さを計量することであった。もし、その方法のポイントを知るためには、われわれは比重と置換の原理の抽象的な公式に頼らなければならない。それを知らなければ水中で王冠を計ることは単なる奇行でしょう。しかしそのポイントが把握された途端に、ヒエロ王と彼の王冠のことは科学的重要性において小さな歴史の出来事ではなくなり、そして、物語は閃きの普遍的なものとして劇的に表現されるに至った。と言うのも、もし閃きが具体的な問題から生じたとしても、もし閃きが具体的なことにその価値を示すとしても、閃きは閃きの起源よりも、より重要で偉大なそしてより広い関連性を有しているからである。そのわけは、閃きが具体的なことを参考にして生じたとしても、幾何学者は図を数学者がペンと紙を必用とし、先生は黒板を必用とする。生徒は実験を自分自身でしなければなりません。医者は患者に会わなければなりません。調停人は問題の場所まで出向かなければなりません。メカニカルな傾向の人は物がどのように働いているかを知ろうとして分解します。しかし、閃きのもつ重要性および関連性はいかなる具体的な問題あるいは応用を超えているが故に、人々は数詞やシンボル、技術的専門用語や公式、定義や公理並びに結論などでもって抽象的科学を系統立てようとしている。かように、まさにその本質から閃きは媒介者であり、要であり、枢軸なのです。それは、感覚と想像力の世界の具体化への閃きなのである。なお、閃きによって分かること、閃きが理にかなった想像的な提案に加えるものは、抽象的で難解な科学の系統的記述のなかでその妥当な表現を発見するだけである。
第五に、閃きは人の心の習慣的特性に関することに移ります。アルキメデスが彼の問題を解決することができる前に、彼はインスピレーションの瞬間を必用としました。しかし、彼が王のもとに解決策を申し述べるときには更なるインスピレーションは必用としませんでした。人は分かるやいなや、分岐点を超えて行きます。ほんの少し前には解決できなかったことが、いまや信じられないほど単純で明らかになります。さらに、その単純で明らかな状態は残存する傾向があります。たとえ最初の閃きの発生がどんなに困難であったとしても、それに続く繰り返えされる閃きは自由自在に起こります。また、これは閃きの一般的な特徴であり、実のところそれが学習を可能にしている。われわれが学ぶことができるのは、われわれは閃きに閃きを加味し、新しいものが古いものを押しのけないでそれを結びつけることができるからである。反対に、学習する主体が一連の閃きのすべてを獲得しようとするならば、学習のプロセスはおいておおよそ不安定に手探りする、そしてどこに行こうしているのか分からない、何について大騒ぎしているのか把握できない、そんな闇の中での初めての時期として記される。そして、人は理解し始めると、徐々にではあるが、最初の暗闇は順々に光、信頼、関心、吸収を増加させる時期へと代わります。そして、微分積分学および理論物理学および哲学の成果が、人々が思っていた不可解で霧がかった領域を無くす。わずかに、われわれは助けの無い幼稚な初心者から、適度に自信のある大学生へと変化して行く。結局、われわれは先生の役割を引き継ぎ、分かる人には全く簡単で明白なことが分からないような生徒の著しい鈍感さに不満を言うことができるようになる。
2.定 義
あらゆる学生が知っているように、一つの円は中心から等距離にある同一平面上の点の軌跡である。すべての学生が知っているというわけではないものは、オウムがするようにその定義を繰り返すのと、賢く定義を述べるのとの違いである。そこで、非常に単純なものを理解することの重要性に関するデカルトの強調に対し謝意を示し、円の定義の起源について探求しましょう。
2.1 手がかり(ヒント)
大きな中心軸、頑丈なスポーク、しっかりした縁のある車輪をイメージしてください。質問しますが、なぜそれは丸いのですか。
質問の意味を限定すると、答えて欲しいことは、車輪が円形であることについて内在する理由もしくは根拠についてです。それゆえに、正解はカート、荷車で運ぶこと、輸送、車大工、あるいはそれらのツールと言った新たなデータを提起することではありません。それは、単に車輪について述べているに過ぎません。
示唆しているものを考えてください。車輪はそのスポークが等しいので丸いのです。中心と縁の間が等しくない場合でも、スポークは等しくあり得ただろうか? それは明らかにあり得ない。さらに、縁は連続するスポークの間にあってフラットでした。
まだ、手がかりはあります。中心軸を点ほどに小さくしてみてください。縁とスポークを線ほどに細くしてみてください。そして、スポークを無限に増やして完全に等しくすれば、縁は完全に丸くなるでしょう。反対に、どのスポークも等しくないようにすれば、縁はコブやヘコミができるのを避けられないでしょう。それゆえに、われわれは、軸の中心から縁の外側までの距離がいつも同じであるがゆえに、車輪は必ず丸いと言うことができます。
今まで述べたいくつかの事項は、順序よく進んでいます。上記のことは、われわれを円の定義にほぼ近いところにまで連れてきています。しかし、われわれの目的は閃きを達成することであり、円そのものに向かってではなく、円に向かっているときの閃きから例示された行為に関するものである。
それで、最初の考察は、点(ポイント)と線(ライン)をイメージすることができないことです。人は非常に小さな黒点(ドット)をイメージすることはできます。しかし、黒点がどんなに小さくても、大きさがあります。点(ポイント)というものには大きさがありません。点(ポイント)に達するには、一切の大きさを無くさなければなりません。すべての量がゼロである黒点(ドット)です。人はとても細い糸をイメージすることはできます。しかしどんなに細くても糸は太さ(幅と奥行き)と長さがあります。線(ライン)に達するには、すべての太さと長さのイメージをゼロにしなければなりません。
2.2 概念(考え方)
第二の考察—点と線は概念である。
まさに、想像がわれわれの欲求とわれわれの恐れが働く場であるように、概念はわれわれの知性が働く場である。まさに、想像は決して見ることができない、聞くことができない、あるいは感じることができない物を作りだすことができるのと同じように、概念もまた想像することすらできない物を作り出すことができる。どのようにして作り出すのでしょうか。それは仮定することによってです。想像された黒点(ドット)は大きさともに位置というものを持っています。しかし、幾何学者は「位置だけあると想像しましょう」と言います。想像された線は幅とともに長さを持っています。しかし、幾何学者は「長さだけあると想像しましょう」と言います。
位置だけ、長さだけと言うような狂気じみたことにも筋道はあります。われわれのイメージや特に夢は非常にランダムな出来事に思えます。しかし、心理学者はそれらを説明することを申し出ます。同様に、概念の基礎となっている仮定には非常に空想的に見えるかもしれないが、それでもそれらはまた説明可能である。なぜわれわれは中心軸を点(ポイント)まで縮小させ、スポークと縁を線(ライン)まで縮小させる必用があったのでしょう。それはわれわれが手がかり、すなわちスポークを同じにする、それもすべてのスポークに求めたことに価値があります。中心点がどんな大きさでも持った限り、スポークは等しくは無くなりその価値を下げてしまう。スポークがどんな厚みでも持った限り、車輪の端は(丸ではなく)平らな物になる。それで、われわれは大きさの無い点と厚みの無い線を想像することで、完全に、必然的に丸くなるようなカーブを求めることができた。
それから、概念の二つの特性について注意してださい。第一に、概念は、仮定すること、考えること、考慮すること、公式化すること、定義することなどの単なる作用によって構成されていること。そして単なる作用以上であるかもしれないし、以上でないかもしれない。もしそれ以上であるとすれば、その作用は単なる概念ではありません。そしてもし、その作用が想像すること、考慮すること、考えること以上でなくても、なお概念として構成するのに十分である。第二に、概念はランダムには発生しません。考え、仮定し、考慮し、定義し、公式化する中で出現します。そして、その多くの名付けられた作用は、ランダムではなく、閃きの行為を伴う結びつきのあるものとして出現する。
2.3 イメージ
第三の考察—イメージは閃きにとって必用である。
点(ポイント)と線(ライン)はイメージすることができません。また、必要性あるいは不可能性と言ったこともイメージできません。さらに、円の定義に接近する際にも必用性および不可能性に若干の不安がありました。われわれが指摘したように、すべての半径が等しければカーブは完全に丸くなければなりません。そして、もし半径が等しくないならば、カーブはコブやヘコミができるのを避けられないでしょう。
さらに、問題にしている必要性は、一般的な必要性ではなく、半径が等しいことにより生じる丸みの必要性についてである。同様に、問題にしている不可能性は、抽象的な意味での不可能性ではなく、半径が等しくないことにより生じる丸みの不可能性である。中心点、半径、カーブのイメージを無視してください。それで把握しているすべての丸みについての必要性や不可能性が消えるでしょう。
しかし、その把握は閃きの本質を成すものです。その把握の存在が、オームのように円の定義をくりかえすことと、賢く定義を述べることとの違いを作り出す。そして、自分で新しい定義を作る能力を持つことになる。
ということで、閃きのためにイメージは必須となり、逆に、閃きが、イメージされた等しい半径と、他方完全に丸く見えるに違いないカーブとの関係を理解するために作用をする。
2.4 質 問
第四の考察—質問に注意を向けること。
質問は口に出して表現されます。「なぜ、車輪は丸いのですか」というように。
その言葉の裏に、『車輪』、『丸い』など、意図的な概念の作用が含まれている。
それらの概念の裏に、人が『車輪』、『丸い』といった言葉の使い方を把握する上での閃きがあるかもしれない。
しかし、われわれが捉えようとしているものはそれとは違っています。「なぜ?」と言うのはどこからやって来るのでしょうか。そのことは何を明らかにし、何を表しているのでしょうか? 丁度、われわれは、発見の喜びで心理的緊張が開放されることについて話すときが来ました。それはその緊張、その動機、知りたい欲求、初めての『なぜ』の本質を成すものについてです。あなたが気に入る名前を付けてください。それは、心、知的好奇心、探求の精神、活動的知性、知ろうとする動機などなど。どんな名前の下ででも、同じことです。そして、私が思うには、あなたに非常になじみのあるものです。
それから、この根源的な動機こそが、純然たる問題です。それは、いかなる閃き、概念、言葉にあっても、その前にあるものです。閃き、概念、言葉は答えに関係しています。そして、われわれは答えを探す前にそれら(閃き、概念、言葉)を求めています。そのように求めることが純然たる問題なのです。
他方、その純然たる問題は閃き、概念、言葉の前にあるけれども、経験とイメージを前提としている。まさしく、閃きが具体的に与えられたもの、あるいはイメージされたものにあり、だから、純然たる問題も具体的に与えられたもの、あるいはイメージされたものについてあります。アリストテレスがすべての科学と哲学の始まりであると主張したのは、驚きです。誰も疑問を持ちませんが、われわれはいくつかの疑問を持っています。
2.5 定義の起源
第五の考察—定義の起源となる契機(モーメント)を区別すること。
動物はする事が無いときには、眠りにつきます。人間はする事が無いときには、疑問を発するかもしれません。最初の契機はその人が知性に目覚めることです。それは生物学的に優勢な動機からの開放と、決まりきった日常的な生活からの開放です。それは疑問、知りたいという欲求の現実的な現れです。
第二の契機はヒント、暗示、手がかりです。閃きが始まったとき、われわれは何かを掴んだのです。われわれが正しい道を歩むチャンスなのです。想像してください。
第三の契機は過程です。想像は他の心配事から開放してくれます。それは自由に知的努力と協働します。その協働は知的な仮定と平行して進めることで成り立ちます。と同時に考えられる領域の近くにあって、仮定を一定の範囲に自制したところに成り立ちます。(101207 start)
第四の契機は達成です。それらの協働によって、また継続的な調整、質問と閃きによって、イメージと概念は中身のあるものとしてその姿を表す。答えはいろいろの形式の概念の一組です。イメージは引き寄せられて概念に近づこうとする。概念は、更なる概念上の限定が加わって、単に類似的なイメージとの違いを明らかにする事ができる。イメージと概念の間の旋回軸は、閃きです。そして、閃き、イメージそして概念が達しなければならない標準的なものを決定するのは、質問、知りたい欲求であり、それが必要条件を満たさなければ更なる質問を続けるであろう。
2.6 名義的定義と説明的定義
第六の考察—異なる種類の定義を区別すること。
ユークリッドが直線を両端の間に真直ぐにつながる線と定義したように、彼は円を一つの完全に丸い平面のカーブとして定義できたかもしれない。それらの定義は間違いなく直線、円という名前の適切な使い方を定めるのに役立ったかもしれない。しかし、実際にはユークリッドの円の定義は円の名辞を適切に使う以上のことを含んでいる。すなわち、いかなる円も全ての半径が正確に等しい、という言明を含んでいる。もし、定義の中に言明が含まれていなければ前提・仮定として付け加える必要がある。
同じ問題を違う観点からみるために、ユークリッドは全ての直角が等しいことを仮定しました。そして二つの隣接する直角の和を平角(180°のこと)名付けた。そうすると全ての直角が同じであるならば全ての平角は等しい。逆に全ての平角が同じであるならばすべて直角は同じでなければならない。さて直線が本当に真っすぐであれば、つまりどの方向にも曲がらないのであれば、全ての平角が同じでなければならないのか? 円の定義に半径が等しいという仮定が含まれているように、直線の定義に平角が等しいという仮定が含まれているのだろうか?
いずれにしても、名義的定義と説明的定義には違いがあり、名義的定義は単に名辞の正しい使い方を言うだけであるが、説明的定義にはそれ以上の多くのものを含んでおり、もし含んでいなければ前提・仮定として付け加える必要があります。
何がその違いを作り出しているのであろうか。それは説明的定義が閃きを前提とし、名義的定義はそれを含んでいない、ということではない。なぜなら言語は大変複雑なツールで、大多数の有意な組み合わせを可能にする、ほとんど限りない多様なパーツを持っているからである。他のツールがどのように正確に効果的に使われるべきかを知るために、閃きが必要であるとするならば、同じように言語についても正確に効果的に使うために閃きが必要である。
それでも、私が思うに、このことが我々の質問に答えをもたらしてくれるでしょう。名義的および説明的定義はともに閃きを前提とします。ところが名義的定義は言語の正確な使い方に関する閃き以上のものは前提にしない。他方、説明的定義はその言語が指示している対象に対する更なる閃きを前提にする。円という名前は、直線という名前が両端の間にある線として定義されるのと同じように、完全に丸いカーブとして定義される。ところがそこからさらに、円の半径は全て同じである、あるいはすべての直角は同じである、と言明すると、単なる名辞の話ではなくなる。名辞が指示する対象についての言明をしていることになる。
2.7 基本的単語
第七の考察—基本となる単語、という古くからの難問への注釈を加えること。
全ての定義が他の単語を前提にしている。それらが定義されうるならば、その定義が更なる単語を前提にするだろう。けれども無限に進むことはできない。従って、定義が定義されない単語に基づいているか、あるいは単語がお互いにほとんど自分自身で定義するような循環の中において定義されているか、のどちらかであるである。
幸いなことに、我々はこの議論の仮定を受け入れる必要はない。定義が私的な空間に起こるわけではない。定義は経験、イメージ、問いかけ、そして閃きと結ばれて出てくる。全ての定義が多くの単語を伴うというのは十分に真である。けれども、いかなる閃きも一つの単語で表現できないということも真である。そして全ての閃きがその前に閃きを必要条件とするものでもない。
次のように言える。つまり全ての基本的な閃きには、単語が関連を定め関連性が単語を定め、そして閃きが両方を定めるような単語と関連性の循環がある。想定された平面上の曲線の完全な丸としての必要十分な条件を把握することができたら、円だけではなく点、線、円周、半径、平面、そして同等性を把握することになる。全ての概念は、一つの閃きを十分に表現するために必要であるが故に、運命をともにするものであり、全てが首尾一貫したものである。その首尾一貫性は、全てが一つの閃きから一緒に結びつけられたが故である。
今一度、基本的な閃き(のワンセット)がありうる。例えば、ユークリッドの幾何学の基礎をなす閃き(のセット)のようなものである。閃き(のセット)が首尾一貫したものであるから首尾一貫した定義(のセット)を生み出す。定義のさまざまな対象が類似した要素によって構成されているから、点、線、表面、角度のような単語が、それぞれ異なる定義に繰り返しでてくる。従って、ユークリッドは自分の理論の説明を、イメージ(のセット)、閃き(のセット)、定義(のセット)から始めるのである。彼の定義のあるものは単に名義的であり、あるものは説明的である。そしてあるものは部分的に名義的に演繹されたものであり、あるものは部分的に説明的に定義された単語から演繹されたものである。
2.8 暗黙の定義
最後の考察—暗黙の定義という概念を導入すること。
D.ヒルベルトが現代の論理学者を満足させる幾何学の基礎論を作りだした。彼の重要な仕組みは暗黙の定義という名前で知られている。そこで、点と直線の意味が、それら両者と二つの点のみが直線を定めることとの関連性によって決定づけられている、という。
この分析に従って言えば、暗黙の定義とは名義的定義なしの説明的定義であると言えるかもしれない。それが説明的定義であるのは、二点の関連性が直線を定めるということが、円において全ての半径が同等であるということと同様、前提条件の一要件である、ということだからである。それは名義的定義を省いていることになる。なぜなら、ヒルベルトがいう点は、ユークリッドがいう位置があっても量がないという意味に限定されないからである。順序づけられた数字の一組が、ヒルベルトがいう点の暗黙の定義を満たすことになる。なぜなら、そのような数字の二組が直線を決定するからである。同じように、一次方程式はヒルベルトの直線の暗黙の定義を満たしている。なぜなら、そのような方程式が二つの順序づけられた数字の二組によって決定されるからである。(解説;①x・y座標でのA点の座標とB点の座標、②ax+b=cのグラフは直線。要するに、点とか線とかの名義的定義は不要である。)
暗黙の定義の重要性はその完全な一般性にある。(解説;ax+b=cでは、a、b、cはどんな数でも良い。)名義的定義の欠如は、まず最初に思考を発生させた対象についての限定の欠如である。説明的あるいは前提条件の要件を独占的使用することが、全体的な科学的重要性を包含する関連性(のセット)に集中させることになる。
3.より高い観点
閃きの本性について解決するために採らなければならない次の意味あるステップは、発展について分析することである。一つの閃きが、孤立したものとして起こるか、あるいは関連性のある閃きとして一定の分野において起こる。後者の場合には閃きは他の閃きと組み合わさり、寄せ集まり、結合して一つの全体にまとめ上げられる。定義、仮定、演繹のセットに根拠を与え、具体的ケースにも幅広く適用できる。しかしそれだけでは終わらない。さらに一層の閃きが起こり、前の見解の欠点が見つけられて、新しい定義と仮定が考案され、新しくてより広い演繹の領域が開かれ、より広範でより正確な適用の領域も広がる。そのような閃き、定義、仮定、演繹、適用などの全体構造の複雑な変化を、より高い観点が生じたこと、と簡潔に言えるであろう。私たちの疑問は、そのとき(より高い観点が生じたとき)何が起こるかということである。 (101207_1:08:12)
単純なことを理解するが大変であるというデカルトの主張からヒントを得て、私たちは算数から代数学の初歩に至までの過程をその案内例として取り上げる。さらに誤解を避けるために算数は小学校で学ぶということを、そして初歩の代数学は中等学校で学ぶということを明らかにしておいた方がいいであろう。
3.1 正の整数
まず始めのステップとして、1、2、3、4、...という正の整数について何らかの定義を作ることから始めよう。
‘1’という単位量の多くの具体的なものからなる全体を仮定しよう。そこで羊やものを数えたり、並べたりする働きなど考えていいでしょう。
さらに、1、プラス、等しい、といった概念は誰にでも知られているから、定義はいらないことにしよう。
それで、整数の無限級数のための無限の定義が続くが、それを次のようにシンボル的に示すことができる。
1+1=2
2+1=3
3+1=4、
などなど、などなど、などなど。(順に1をプラスして無限に続く整数が考えられる。)
このシンボル的な表示はさまざま仕方で解釈できる。たとえば、1に1をプラスすると2になるとか、2は1より1だけ大きいとか、あるいは第2番目は1番目の後に来るとか、あるいは1、2、3、などなど、各要素のグループのクラスの関係さえ意味する。鋭い読者には、上に並べられた定義の重要な要素は、“などなど”、であるということに気づくであろう。それがなかったなら正の整数が定義され得ない。つまり正の整数は不定に広がっていく多数のものであるが、それが無限級数になりうるのは、“などなど”という一定の表現が伴うときだけである。では、“などなど”とはどのような意味を持っているのだろうか。それは何らかの閃きが起きたはずである、という意味である。関連性のあるそうした閃きがあって、その意味に目覚め、定義する働きがはてしなく続けることができれば、もはやそれ以上に何も話す必要がない。しかし生徒がそれを理解していないならば、気の毒な教師は分かりきったことを繰り返すしかない。なぜなら、正の整数を定義するには閃きに頼る以外に他の道がないからである。
ところで、既に明らかにされたことを思い起こすのは悪くない。すなわち、一つの閃きは多くの概念で言い表せたということ。今回の例では、一つの閃きが無限の概念を作り出している。
3.2 加法の表
第二に誰からもよく知られている等しいという概念を思う少し精密なものにしよう。まず、等しいものに等しいものを加えるなら結果は等しいとしよう。さらに1は1に等しいとしよう。それだけで加法の表の無限級数が作られる。
2を加えるための表は、正の整数を定義する等式の両辺にそれぞれ1を加えることによって作られる。すなわち以下の通りである。
正の整数の定義から 2+1=3
両辺に1を加えると
2+1+1=3+1
それで新しい表ができる 2+2=4
このように2を加える表が作られる。このように表が作られると、3を加える表が作られ、さらに4、などなどを加える表を作ることが可能となる。ここで、などなどとは何らかの閃きが起こったはずである、という意味である。
こうして、正の整数の定義と、等しいものに等しいものを加えるという仮定から、果てしなく広がる演繹的展開が導きだされうるのである
3.3 同質的展開
第三に、同質的展開ということに進んでみよう。よく知られている加法という概念は、乗法、累乗、減法、除法、ルート(乗根)といった更なる概念によって補完される。しかし、これらの演算の展開は同質的なものであり、既に使用されてきた概念に含まれており、意味の変化はない。
そうした意味で、乗法は一つの数を何回も加算することである。たとえば5×3は、5を3回加算するという意味である。同様に、累乗は一つの数を自ら何回も乗法することである。たとえば5の3乗は、5×5の結果にもう一度5を乗法する(5を3回乗法する)という意味である。他方、減法、除法、ルートは演算を出発点に戻す逆向きの演算を意味する。
指摘する必要がないと思われるが、いくつかの閃きによって、加法の表から乗法や累乗の表が作られうる。同様に、加法、乗法、累乗の表から減法、除法、ルートの表が作られうる。
このように、同質展開ははじめの演繹的展開を発達させ、非常に大きな展開を構成する。同質的展開は、新しい演算を導入する。ただ、新しい演算が元の演算の意味に変化をもたらすことはない。
3.4 より高い観点の必要性
第四に、より高い観点の必要性を発見することについて述べる。その発見は、逆向きの演算が出発点に戻って、一般的に最大限まで許されたときに生じる。そのとき、減法は負の数の可能性を示し、除法は分数の可能性を示し、ルートは無理数の可能性を示す。さらに、演算の意味についての疑問が生じる。すなわち、負の数や分数、無理数を乗算するとき、乗法は何の意味があるのだろうか。負の数を減算するとき、減法は何を意味しているのだろうか、などなどである。本当のところ、“1”や“等しい”という意味も分からなくなる。なぜなら、循環小数0.9999……が1に等しいということが示されるからである。
仮に x = 0. (0.9999………)とする
(0.9999………)とする
それで 10 x = 9.
よって 9 x = 9(10 x – x =9 x、 9. − 0.
− 0. =
9 )
=
9 )
従って x = 1
3. 5 より高い観点の定式化
第五に、より高い観点を定式化してみよう。
まず、(1)規則、(2)演算、(3)数、に区別しよう。
数は演算によって絶対的に定義されるとしよう。それは、全ての演算結果が一つの数となり、いかなる数も演算の結果となりうる。
さらに、演算は規則によって絶対的に定義されるとしよう。それで、規則によって行われたものごとは演算である。
要領は、数を定める演算、そして演算を定める規則を発見することである。
より高い観点を発見するには、この要領を実行することである。それは(1)演算が古い規則によって行われていること、(2)新しい規則の公式化の中に表現されること、という一定の閃きの中に存在する。
もう少し説明しよう。われわれは車輪のイメージから、閃きによって円の定義へと進んだ。しかし、車輪は想像することができたが、円は一定の点と一定の線で構成され、そのどちらも想像できないものである。したがって、車輪と円は単に類似しているだけで同じではない。さて、算数から初等代数学への移行は似たようなもものである。つまり、車輪のイメージを「算数をする」というイメージに置き換えればよい。こうしたイメージは、同質的展開の規範にしたがって数を書いたり、加法、乗法、減法、除法したりすることを含む膨大で、ダイナミックで、仮想的イメージである。このイメージ全体は一度に思い描かれるものではなく、部分的にでも画かれうるもので、人がそれに備えて準備しているときには関連性のある部分が浮かび上がってくるであろう。そして、この膨大で仮想的なイメージの中で演算の仕方を定める新しい規則が把握されるはずである。新しい規則は古い規則と同じものではない。新しい規則はより均整のとれた、より精密で、より一般的なものとなろう。つまり、新しい規則は、精密で均整のとれた円が車輪とは異なるように、古い規則とは異なるのである。
新しい規則とはどういうものなのであろうか。学校では分数の規則が一般化され、正・負の符号の規則が導入され、方程式や指数の規則が明らかにされた。その結果、加法、乗法、累乗、減法、除法、ルートという概念が再定義されるようになった。そうした演算の再定義の結果、新しい数が加法だけによるのではなく、どの演算によっても生じうるということが明らかになったのである。
3.6 連続するより高い観点詳
(101221 start)し
読者は、規則による演算の定義、および演算に基づく数、
4 逆の閃き
直接的な閃きや、同種の閃きの集まりや、より高い観点のほかに、数は少ないが重要な逆閃きというものもある。これらは、直接的な閃きと同様に、感覚により得られた、あるいは想像により表現された肯定的な対象を前提としている。直接的な閃きが理解しようとする知性の自発的な努力に応えようとするが、逆閃きは理解可能性の程度、レベル、種類が異なるものを区別するところのより繊細で批判的な知的態度に応じようとする。直接的な閃きは、捉えるべき要点を把握したり、ある問題の解決を見いだしたり、明らかにすべき理由を知らしめたりするが、逆閃きは、何らかの方法で捉えるべき要点がないという要点、解答がある筈がないという解答、現実の合理性が区別され限定されるという理由を把握する。そして結論として、直接的な閃きの概念的説明は、たとえ予想されていた経験的な要素を否定しても、一つの理解可能性を肯定する。それに対して、逆閃きの概念的説明は、予想される理解可能性を否定しても、経験的な要素を肯定する。
最後に述べた点はきわめて重大であるから、より一層磨きをかけることを試みましょう。理解可能性とは、直接的な閃きによって捉えられる内容を意味する。それは、われわれが理解しない限りは私たちの認識にならない要素であり、この章の始めに述べた簡単で分かりやすい方法で理解することで、われわれの認識に加えられる要素である。さて、そのような理解可能性は、もう既に獲得されているか、あるいはただ予想されているかのどちらかである。既に獲得されている理解可能性を否定することは逆閃きの結果ではなく、以前の直接的な閃きの単に修正すること、つまり、その閃きに不十分な点があることや、未解決の問題を残していることを認めることである。しかし、予想された理解可能性を否定することは人の知性の自発的予感に逆らうことであり、答えではなく問いのあら探しをすることである。論証的科学の観点から考えると、予想された理解可能性を否定することは、一定のタイプの問いには答えることができないということを証明することである。さらに、経験科学の観点から考えると、予想された理解可能性を否定することは、一定の問いが答えを持っていると想定することが誤りである、ということを指摘する適切な理論や仮説を提出することである。結論として、逆閃きの発生が、何らかの否定的な概念によって規定されたということではない。たとえば、「非赤」、「大きさのない場所」、「非発生」は、それぞれ「赤」、「大きさ」、「発生」を取り除いたものである。しかし、これら後者の用語はわれわれの認識の経験的な構成要素を示すものであり、可能性や必然性、統合や関係、直接的な閃きによって知りうる理解可能性などを示してはいない。
逆閃きの一般的概念はまさしく簡単で明白ではあるが、異なったグループの読者に満足してもらえるような実例を先に示すことが簡単ではないので、私は苦しんでいるところです。さらに、すべての閃きは概念的な情景の中にあるが、その概念を通して伝達および議論が行われる。それ故に、読者がその根底にある閃きよりむしろ概念に注目するであろうという危険性がいつでもあるとともに、把握すべき論点がないことだけを閃きによって把握する場合に、その危険性は相当増大させられる。よりいっそう悪いことに、逆閃きは人間の思想がはるかに大きく成長した場合においてのみ起こりうるものである。それらの内容の表明は、後のシステムにおいてそれらの否定を利用しなければならない。その後のシステムにおける成功は、まさしく、知性の一層の自然発生的な予感を排除するルーチンを引き起こす傾向がある。そして、逆の閃きの重要な特徴を確立し、しばしば不確かな歴史の証言者として訴える必要があるかもしれない。その複雑さの真只中において、読者が達したところの了解度の自然発生的な期待が、それと反対する少しの言葉だけの警告よりも大いに勝るべきであり、そしてそれが起こるとき、逆の閃きの説明が本当に分かりにくいものとなる。したがって、実例をあげることに何も困難はないが、自明のことについて予備的な説明をすることが賢明だと考えました。
逆の閃きの最初の例として、古代の人が非公約量と呼び、現代の人たちが無理数と呼ぶところのものについて取り上げてみよう。その両者に、「量」や「数」という言葉によって指摘されている対象がある。さらに、そのなかには「非」や「無」という言葉によって暗示さている否定的な要素もある。要するに、どちらの場合にも、否定は人間の知性の自発的な要素と関連している。つまり、「非公約量」は、一定のものさしが一定の諸量に適応される可能性を否定している。そしてアリストテレスは、そうした否定を一見大きく驚きのある問題とみなした。「無理数」はより一層、一定の諸数と人間の理性との一致を否定しているのである。
関連性のある閃きを指摘するために、「無理数とはなぜ無理数なのか」という問いを出そう。本来この問は、「なぜこの車輪は丸いのか」という問いに似ている。しかし、こうした問いが導いた解答が、車輪に内在している理解可能性を言い表したのに対して、今度の解答は、無理数が人から予想される理解性を有さないということを示すのである。
たとえば、√2は、1より大きく、2より小さいある値である。その値はm/nのような仮分数に相当すると予想されるだろう。そこでのmとnは正の整数であり、共通因子(公約数)を取り除けば、それらはつねに互いに素数となりうる。さらに、こうした予想が正しければ、正方形の対角線と一辺は、それぞれ共通の単位量のm倍、n倍である。しかしながら、それは正解からほど遠く、矛盾へと進んでいく。なぜなら、もし√2=m/nが正しければ、2=m2/n2も正しい。しかし、mとnが互いに素数であれば、m2とn2も互いに素数となるはずである。その場合、m2/n2は2やそれ以上のどのような整数とも等しくなりえない。この議論を一般化すると、無理数が無理数と言えるのは、それが知性の予想する有理数の分数と異なるからである、ということができる。
逆閃きの第二の実例は、(26:58〜31:40)数えられない多数の量がある。そこには積極的な対象があり、多数である。そして、消極的な限定があり、数えられないということである。さらに、“数えられる”という単語は、広く捉えられる場合、つまり全ての整数、全ての有理数、そして論証できるすべての代数学的実数を含む。さらに、数えられない量から数えられる量をさし引くと、数えられない量が残るということが示される場合には、自然に0から1の間にある全ての数が数えられる量であると推定される。実際、無限小数は数えられない量であることが示される。0から1までの代数学的分数は、その間の実数の無視できる部分であるという結果が出てくる。
第三の実例として、実験科学を見ると、ニュートンの運動の第一法則の意外な点について考えてみよう。すなわち、物体は外部からの力により変化させられない限り、一直線上の等速度運動の状態にあり続ける、という法則である。
この宣言と文脈の中に、逆閃きの体系的な三つの特徴を見分けることはさほど難しくはない。つまり、第一に、現実の対象物、すなわち等速で直線運動を続けている物体がある。次に、否定である。すなわち等速度を維持していることは、外部の力の作用によるのではなく、そのような作用がない、ということである。なぜなら、加速度がない限り速度は一定に保たれるが、外部の力の合計が0でなくなれば、加速度が生じる。最後に、外部の力の否定は人間知性の自発的な予想に逆らうものである。なぜなら、人は普通、等速運動は静止の状態と同様のものではなく、外的原因による変化であると考えるからである。
しかしながら、幾人かの読者はこの問題についてより細かく論ずることを望み、次のことに同意するでしょう。それは外的原因の必要性が、アリストテレスの天体運動、投射物運動、そして真空での運動などの理論によって強調されてきた、ということです。しかし、かれらはアリストテレスの見解が、少なくともジョン・フィリポヌスの時代から否定されてきた、ということを付け加えるでしょう。このアリストテレスの考えに反対する見解では、投射物は外的力ではなく、なんらかの内的な本源か、原動力か、属性か、特性か、あるいは他の内的な根拠によって運動が保たれている。最後に、かれらは、ニュートンが慣性状態の連続性を説明するために、物質が本来有している内的な力に訴えたのではないということが、確かかどうかを問うでしょう。
今、明らかに、ニュートンの解釈が現在私たちがやろうとしている事柄ではない。言わなければならないことの全ては、逆閃きが外的な力による説明の代わりに内的な力や特性による説明に置き換えても説明にならない、と言うことである。というのも、その場合には、前者のそのままの閃きが後者のそのままの閃きによって修正されただけであり、同時に、人間知性の自発的な予想が一つの方向においてブロックされ、ほかの方向の出口を与えられただけである。
逆閃きの例のために、前者のことを再度取り上げることなしに、後者の出口をブロックすることが許されるだろう。疑いもなく、私たちは、外的な原動力や力が否定された場合、真の説明を与えるところの何らかの本来的な特性があるに違いない、と自然に考えるだろう。しかし、外的な原動力や力による説明が実験に基づいて検証できるのに対して、何らかの本来的な特性による説明は、何らかの「物質に内在する力(vis matereriae insita)」を科学的声明としてはほとんど看做されないのである。もし、加速度がゼロである場合は関連する外部の力の合計もまたゼロである、と言えば、その発言は普通の検証において認められる。しかし、物質の本来的な特性が外部の力の作用を不要とする、と主張するならば、科学者は神秘的な原因に訴えることはできない、ということを気づかされる可能性が高いでしょう。
さて、こうした抗弁が決定的とみなされるなら、逆閃きの例に達したことになる。質問の対象となる積極的な物体がある。それは等速運動の状態を保つ物体である。そして、等速運動が連続しているのは、外部からのいかなる力によっても説明できない、という否定がある。最後に、この否定は自然科学にとって決定的である。なぜなら、科学は既知の法則からはっきりしない性質、特性、属性、力などその他同種のものの専門用語の秘めた説明を推論しようとしないからである。
第四の逆閃きの実例は、(32:01〜)特殊相対性理論の基礎的前提から得られるかもしれない。その前提自体は物理学的原理、法則の数学的表現は慣性の変換の下でも変わらない、ということです。われわれの説明に達するためには、物理学者が物理学的データを理解するために努力しているときに前提に訴えるが、われわれはその前提の具体的な意味を理解するだけで足りる。
その探求の積極的対象はそれがデータで構成される。そのデータは次の二つが考えられる。(1)最初の座標K、(2)そしてもう一つの座標K’、これは座標Kと変わらない速度の関係にある。
積極的対象の概念化における消極的要素が、「不変」という言葉によって指示されている。その意味は、一つの座標からもう一つの座標に変わるということが適切な物理学的原理および法則の数学的表現の形態におけるいかなる変化をも導かない、ということである。けれども数学的表現の形態が変わらなければ、数学的に表現された理解可能性は変わらない。そして理解可能性に変わりがなければ、理解可能性を把握し数学的に表現する理解という行為に変わりがない。したがって、その前提の具体的な意味は、データが熟考されている時空的観点に差異があるにもかかわらずデータを理解する行為には差異がない。データを把握する一般的理解可能性には差異がない。そして、理解可能性の数学的表現には差異がない。
最後に、データにおいて、あるいは時空的観点において差異があるにもかかわらず、理解の行為には差異がないのはいつものことである。そのようなケースの大部分では逆閃きの機会はない。経験的差異は理解可能な相手であるが、誰も理解可能な相手があると期待していない。こうして、大きな円形と小さな円形の間に経験的差異は見られるけれども、小さな円形と大きな円形の定義が異なること、あるいは、大きな円形と小さな円形の異なる属性を定めあるために異なった定理を誰も期待していない。けれども、このような例がたくさんあるにも関わらす、特殊相対性理論によって仮定されている不変性は、その中にない。それゆえに、その不変性がこの空間と時間のついての普通の考え方を強力に見直すことを暗示し、そして、その見直しに人間知性の自発的な期待は、それに反して強く反抗する。
したがって、要点をまとめると、特殊相対性理論における基礎的な仮定が(1)物理学者たちが考えているデータ、(2)物理学者たちが得られる閃き、(3)その閃きによって達した法則、原理の数学的表現の形態、の3つにおいて具体的に解釈される場合には、次のような三段論法が出てくる。
物理学者の閃きに差異がない場合は、物理学的法原理と法則の数学的表現の形態に差異があるはずはない。けれども、加速度的変化が起こる場合は、物理学者の閃きには差異がない。したがって加速度的変化が起こる場合は、物理的原理と法則の数学的表現には差異があるはずがない。
大前提は、物理学者の閃きと物理的原理と法則との間に対応があるということを仮定する。言い換えれば、理解する行為の中身が誠実に数学的表現の形態に反映されるということを要求する。小前提は、我々の逆閃きを含んでいる。つまり、加速度的変化の差異に相当する閃きの差異を否定している。言い換えれば、物理学全体に関してニュートンが主張した運動の第一法則の変わらない速度の理解可能性の欠陥というものを主張している。最後に、前提が真である時、結論は真で、あり、大前提が単に方法論的な原則と看做されるのに対して、小前提は経験科学の主張であり、仮説と確認の方法を通してのみ確定される。
結論として、すでに言及したポイントを思い起こしましょう。逆ひらめきはいくつかの付加的積極的な文脈においてのみ、その表現が見いだされる。このようにして、変わらない速度の理解可能性の無さはさまざまに異なる文脈において表現された。エレヤ派哲学のゼノのパラドックスが、運動という事実の否定に導いた(そのパラドックスとは、A地点からB地点に向かう運動は、永久に到達しない、という論理。現在では微分積分学で解決する)。存在の哲学という文脈において、アリストテレスが運動の実在性を主張した。しかし彼は、それを不完全な範疇以下の存在とみなした。数学的応用力学の文脈の中で、ニュートンは慣性の原理を主張した。電磁気場におけるクラークマクスウェル方程式の文脈のなかで、ロレンツがその方程式が加速度的変化の下で変わらないままでいる条件を見つけた。フィッツジェラードが運動の方向に沿って物体が縮まるという仮説によって、ローレンツの成功を説明した。アインシュタインが同時性の問題においてジェラードと同じ一般的説明を見出した。そして彼が物理学的原理と法則の数学的表現の変化的属性という方法論的レベルという問題を提起した。最後に、ミンコスキーが4次元の多様性を導入することによってアインシュタインの立脚点を体系化した。疑いの余地は無いが、ゼノンから特殊相対論まで同じような逆ひらめきが働いていた、と推測するのは間違いである。けれどもずっとこの間、局所的運動の理解可能性の否定がある。そして、引き続いて起こる文脈が内容と価値において著しく異なるにもかかわらず、少なくともそれぞれの文脈が同じ方向を目指しており、それらは逆ひらめきが同時に起こる直接の閃きに依存していることを例証している。
5 経験的残滓
逆ひらめきは、相対的にまれなことであるけれども、決して些細なことではない。なぜなら、逆ひらめきは、間違った質問を取り除くのみならず、普通は非常に並外れた意味のあるアイデア、あるいは原理、方法、テクニックなどと関連付けられている。数学的連続体のおかしさから、相対関係と限界の概念を通じて、連続関数と微積分学という天才的な輝きが生まれる。同じように、一定速度についての理解可能性の欠如は、第一級の科学的成果と関連しているところの慣性の法則が、運動の法則としてではなく、非常に小さなより強力な加速度の理論として動的に考えることを可能にした。物理学的原理と法則の不変性が、加速度的変化の下で、極めてきれいなアイデアであるだけでなく、過去の50年間の実り多き豊かさを示してきた。
この意義を探求するために、経験的残滓という概念を導入しましょう。経験的残滓とは、(1)肯定的な経験的データを基礎とし、(2)それ自身の内在的理解可能性を有せず、(3)いくつかの埋め合わせすべき顕著に重要なより高次の理解可能性と関連している。たとえば、個別的な場所と時間は残滓に属している......すなわち、(1)個別的な場所と時間は、事実、経験的に異なる。(2)その「事実」には直接的な閃きによって把握される理解可能性がない。(3)そうした事実は科学的な協力と一般化を可能にしている。具体的な例をあげよう。第一の特性は、真空はデータが無いという限りにおいて、経験的残滓の一部にはなり得ない、ということ。第二の特性の説明には、内在的理解可能性の否定が、経験の否定あるいは描写の否定ではない、ということを思い出すべきである。経験的残滓における構成要素は、積極的に与えられるだけでなく、指摘され、概念化され、名付けられ、尊重され、議論され、肯定され、そして否定される。けれども、その構成要素が、色とか音とか温度とかと同じように与えられたものであるにも関わらず、それについて正確に考えることもでき、流暢に話すこともできるが、それでもそれらが閃きの直接の対象ではない。それらは、横断の波、縦の波、分子的運動、あるいはいかなる他のより適切であると思われる理論的構成によっても説明できない。最後に、第三の特性は、逆閃きおよび経験的残滓が完全な相関関係にあるわけではない、ということ。なぜなら、逆閃きは、アイデア、原理、方法、あるいは特別な意義のある技術との関連によって特徴づけられてはいないからである。いま一度、経験的残滓は、理解可能性の否定によって得られる知性に対する設問の自発性によって特徴づけられたものではない。
これらの違いが、経験的残滓を逆閃きよりもより広い範疇にするのみならず、経験的残滓の議論をより難しくしている。なぜなら、理解可能性が否定された経験の更なる積極的側面を発見する難しさの大部分は、誰もそれらが理解可能性を持っているとは思わない、ということである。
したがって、特定の場所と特定の時間は経験的残滓につきものである。それらが経験の積極的な側面である。そして、それぞれ異なっている。けれども、なぜ一定の場所が別の場所ではないのか、なぜ一定の時間が別の時間ではないのか、とかつて誰も聞かなかったので、人々はこの質問が出されると戸惑ってしまい、そのような質問のばかばかしさとは違う何かが、意味されているに違いないと想像する傾向にある。そして多様な虚構の困難を経験した後で、次のような単純な結論に到達する。それは、(1)特定の場所と特定の時間は事実上、異なっている。(2)その事実に対する直接的な閃きによって把握される内在的理解可能性はない。(110111 start)
たとえば、Aの位置と、Bの位置が目に見えて異なるのは、長さABという距離によって隔てられているからだと、人は言うだろう。しかし、等距離にある3地点A、B、Cを考えてみよう。なぜ、AB、BC、CAの距離が異なるのか。もし、距離の相違を位置の相違によって説明しようとすれば悪循環に陥ってしまう。さらに、三つの距離は長さが等しいために、距離によって異なるとは言えない。しかし、方向性が異なるためにそれらの距離が異なるのだろう、という人もいる。では、なぜ三つの方向性が異なるのか。そして、なぜ平行で等しい距離が異なるのか。ことによると、そのような議論はやりすぎなのかもしれない。いくつかの相違は根源的なものとして認めるべきなのであろう。いづれにしても全てが説明できるわけではない。まさに、その通りである。しかし追加すべきものがある。すなわち、根源的なものは、何かの根源的な閃きの内容ではなく、何の閃きにも合致しない何らかの根源的な経験の内容である。もし、何らかの根源的な閃きの内容があったなら、頭脳明晰で明らかな説明が欠けることは無かったであろう。しかし、特定の場所の相違および特定の時間の相違が、どんな質問や閃きに先立って与えられていたとしたら、またそれらの相違の説明をするどんな閃きとも釣り合わない相違が与えられていたとしたら、経験的残滓というカテゴリーを導入する必要があったのである。
しかし、まだ納得できない人がいるかもしれない。なぜなら、特定の場所や時間は基準座標系によって結び付けることができる。座標軸はすべての場所と時間を指摘し、区別するために用いることができる。そして、あきらかにそのような構造は極めて理知的で、極めて理解可能なものである。さて、疑いもなく、基準座標系は直接的な閃きで感知しえたものであるが、その閃きで把握されるものは、秩序づけられた相違である。その相違は、秩序によって説明されるものではなく単に前提とされたものである。そのように、異なった閃きによって把握される異なった幾何学は、すべてが等しい前提での場所あるいは時間における相違に対して異なった理解可能な秩序を提供する。そして、それは完璧に正しく、何ら説明しようとはしないのである。
さらに、もう一つの側面を指摘しよう。特定の場所そして特定の時間の相違は、それ自身に内在的な理解可能性が含まれていないため、他の理解可能性に何の変化ももたらさない、ということである。そのことは単に場所の相違によるのではなく、異なった場所における異なった観察や異なった実験の結果がもたらす何らかの相違なのである。同様に単に時間の相違によるのではなく、異なる時間に異なった観察や実験の結果がもたす何らかの相違なのである。しかも、そうでなかったならば、それぞれの時間や場所が独自の物理学、化学、生物学などを有していたであろう。しかし、自然科学が一定の場所で瞬間的に成し遂げられるものではないので、そこでの物理学、化学、生物学などは存在していなかっただろう。一方、特定の場所や時間が経験的残滓に属しているため、大きな影響のある科学的協力が現れるのである。すべての場所およびすべての時代における科学者たちは、自分たちの活動がどこでいつ行われたのかに関係なく、共通の蓄えとして彼らの成果を蓄積することができる。
なお、科学的な協力よりも重要なことは、科学的な一般化である。化学者たちは、すべての元素とそれらの同位元素や、それらの化合物を熟知したとき、われわれの宇宙の物質のおよそ55%を構成している水素原子一つ一つのために、異なる説明を見つける必要がないという有難さを忘れていることだろう。しかし、少なくともそうした数多くの説明の必要がないということは、私たちの目的にとって重要な価値がある。すなわち、それぞれの化学的元素とそれぞれの化合物は、ほかの種類のそれぞれの元素及び化合物とは異なるが、その相違を説明する必要がある。一方、それぞれの水素原子がほかのそれぞれの水素原子と異なっていても、相違について説明する必要がない。ここで、明らかに私たちは経験的残滓の別の側面、すなわち個体性という側面を取り扱っている。そして、なお明らかであるが、この側面は、すべての科学的技術にもっとも影響力のある一般化といういとなみに直結しているのである。
ところが、この問題は、プラントン主義者以来の哲学者によって、数学的科学的認識の普遍性を説明するために、永遠で不変の形相とアイデアを前提とすることによって説明する上で、使われてきた。しかし、次の事実によって困惑することになった。それは、永遠で不変な一は、一に一を加えると二になる、という普遍的な言明を基礎づけることはできなかったこと。あるいは、永遠不変な三角形がすべての側面において同じである三角形を定理づけるのに十分ではなかった。このようにして、おそらく単なる数的差異の哲学的問題が生じた。その問題と関連して、抽出という教義に基づいた理論が形作られた。従って、我々はこれらの問題について何かを言わなければならない。われわれが水増ししようと企てていると見えないように、可能な限り手短に言及する。
したがって、単なる数的差異という主張は二つの要素が関係している。理論的側面では、どんなデータの集合も完全に説明されたとき、すべての側面において同じデータの別の集合での異なった説明を必要としない。しかし、事実の側面では、どんなデータの集合も完全に説明されたとき、すべての側面において同じデータの別の集合が存在しないということを定めるには、徹底的な点検によってのみ可能である。
理論的主張の基礎は、同じようなデータの集合が2回目に把握されたとき、その理解の行為はまったく同じである、ということである。したがって、ある人がすべての側面において最初と同じデータの二つ目の集合を把握するとき、同じ理解の行為を繰り返す。したがって、物理学者が、「赤」とか「ブルー」とかについて異なった説明を提供する。彼が赤の異なった色合いについて、異なった説明を提供する。そして、物理学者が、まったく同じ色でまったく同じ色合いの異なった例について、それぞれの説明を探す必要があるという提案に意味を見出さないだろう。
事実的主張はもっと複雑なものである。それは、すべての側面において同じデータの異なった集合が存在している、という主張ではない。それがユニークな実例、宇宙におけるほかの実例に当てはまらない形で説明されるべきであるというユニークな実例、の否定ではない。宇宙においてどの個体物もユニークな実例である、ということの否定でもない。逆に、我々の宇宙に当てはまる説明の本姓に関係する事実がある。つまり、そのようなすべての説明は、一般化され普遍化された要素によって作られているという趣旨である。これらの一般化され普遍化された要素は、複合化され、いかなる個体物も異なった要素のコンビネーションによって説明される。そのようなコンビネーションは、共通の属性の一つのコンビネーションの説明であって、個体性の説明ではない。なぜなら、個体物の個体性が説明されるならば、ほかの個体物が正確に同じような様式で理解されうることを前提にすることは無意味である。他方では、個体物の個体性が説明されていないので、すべての側面においてよく似た個体物が存在するかどうかを、徹底的な審査によってのみ定めることができる。したがって、一つの総合的な進化論に達し、それがこの地球におけるすべての生命の事例をそれぞれ違った説明ができたとしても、厳密的な論理でいえば、われわれはこのすべての側面において同じような進化の実例が存在しなかったということを、全面的に確信が持てる前に、すべての他の惑星を点検しなければならない。
短く言えば、個体物は異なっている。けれども、我々の宇宙において究極的な相違は、直接の閃きによって把握されるものに相当するものがないという事実の問題である。さらに、科学的協力が、特定の場所および特定の時間の経験的残滓の相違に基礎を置いている。そして、科学的一般化は、同じクラスの個体物間の経験的残滓の相違に基礎を置いている。まさしく、最低のクラスのものは、直接の閃きに対する科学的進歩によって発見されるべきである。たとえ、ある意味で、個体物の数だけ多くのクラスがあると証明されたとしても、ただちに、その意味で、個体物の個体性が理解されたというわけではなく、ただ単に、普遍的説明的要素の一つのコンビネーションが、それぞれの個体物における共通の属性あるいは側面の一つのコンビネーションと対応した形で設定できる、と我々が知りうるだけである。なぜなら、閃きにおいて把握された内容は、感覚におけるのと同じように想像においても体現される。そして、感覚において一つ以上の実例が有るかどうかは、経験的点検によってのみ確定することができる。
後で、経験的残滓の更なる側面に注意を向ける予定がある。それは、同時に集まるイベントの経験的残滓の特性に基礎を置いている統計的方法と、そして、人間の無知な意見、選択、行為における理解可能性の欠如ゆえに必要とされる弁証法的方法についてである。しかし、一般的な概念としての経験的残滓は明らかであるので、我々はそれに結び付いた抽出という論題に変えたい。
正確にいえば、抽出は、感覚的あるいは想像的ゲシュタルト(形態)を把握するものではない。共通の名前を使うということでもない。ほかの道具を使う問題でもない。最後に、一回に一つの質問に集中し、一時的にほかの質問を遠ざけることでさえない。正確には、抽出するということは、本質を把握することであり、偶発的なもの無視することである。また、意味のあるものを見ること、見当はずれのものを脇にはずすこと、重要なものを重要と認め、取るに足らないものを無視することである。さらに、質問されたときの答えは、本質とは、有意義なものとは、重要なものとは何なのか、偶発的なもの、見当はずれのもの、無視すべきものは何なのか、の二要素から構成されねばならない。なぜなら、抽出は知性の選択力によるものであり、そして知性は、発展の一定の段階にあると見なされるか、あるいは、ある科学もしくは諸科学のグループが完全に修得されたときの発展の終着点として見なされる。
したがって、本質的なもの、有意義なもの、重要なものは、一定の閃きあるいは閃きのグループに関連して、(1)閃きまたは複数の閃きが起こるために必要なデータの状況のセット、あるいは(2)閃きまたは複数の閃きの表現に必要な関連のある概念のセット、で構成される。他方では、偶発的なもの、見当はずれのもの、無視すべきものは、(1)閃きや複数の閃きに該当しないデータに付随して同時に起こる状況、あるいは(2)単にデータに付随して同時に起こる状況に相当する概念のセット、で構成される。ここでも、本質的なもの、有意義なもの、重要なものは、一つの科学あるいは科学連合の完全な発展に関連して、(1)適切な範囲にあるすべての閃きが起こるのに必要なデータの状況、あるいは(2)科学あるいは諸科学の閃きのすべての表現に関連のある概念のセット、で構成される。他方では、偶発的なもの、見当はずれのもの、無視すべきものは、経験的残滓に存しており、それが自分自身において内在的理解可能性を持っていないので、一つの科学あるいは諸科学のグループが完全な発展に達した時でさえ、説明なしに残される。
最後に、この閃きの要素の章を締めくくるために、この章の内容において、本質的なもの、有意義なもの、重要なものを、簡単に指摘しておこう。他方では付随的なもの、関係しないもの、無視すべきものを指摘しておこう。この章では、本質的なものは閃きに対する閃きだけである。したがって、付随的なものは、(1)実例として選ばれた特殊的な閃き、(2)その閃きの表現、(3)その表現よって再現されたイメージ、である。そのことから、読者は、アルキメデスの物語の代わりに、それよりも名高いものでないがより助けになる自分自身の経験を有益に使うべきである、と言える。読者は、円形の定義の代わりに、知的に理解可能的に行われた他のどんな定義行為でも使うことができる。そして、読者は、その行為が、無難な間違いのない確立された専門用語ではなく、創造的な閃きの一言であるのはなぜなのか、と尋ねるだろう。読者は、初等算数から初等代数への移行の代わりに、ユークリッド幾何学からリーマン幾何学に至るプロセスを評価できるかもしれない。そして、無理数はなぜ無理数なのかと尋ねる代わりに、超越数はなぜ超越数なのかと尋ねることができる。
同じように、慣性の原理が、ニュートンの法則は加速度的変化の下で変わらない、ということを帰結するのかどうか。電磁方程式は加速力的変化のものとで変わらないという閃きを、ローレンツに与えたのは何なのか。逆閃きが、一般相対性理論の基礎的前提を説明できるのかどうか。特定の場所あるいは特定の時間の差異が、全く同種の水素原子の差異のような経験的残滓の同じ側面なのか。いかなる分野においても、本質を極めるために付随的なものを変えてしまうように、人は閃きという概念に親しむために、実例を変えたり、自分自身で自分の言葉の中にそのポイントを発見する。そして別の人は、そのポイントをつかみ、おそらく存在しないだろう平均的な読者に、そのアイデアを伝達できるだろうと考えられる言葉で表そうとする。(110111_終了)